今回はスマトラ島に焦点を当ててインドネシアコーヒーの収穫から出荷、日本へ輸出されるまでをみてみましょう。スマトラ島はバリサン山脈という標高の高い山々が連なっていて、この標高の高さがコーヒー栽培に理想的な環境を生み出しています。この山脈のおかげでスマトラ島の山間部は赤道直下にもかかわらず涼しい気候を保っています。コーヒーの木は20〜25度の気温を好むので、スマトラ島のコーヒー栽培地域は理想的な環境といえます。さらに、火山活動によって形成された水はけの良い肥沃な土壌がコーヒーの木の成長を助けています。それではインドネシアのコーヒーがどのように育ち、収穫され、出荷されるかをお伝えします。

◯コーヒーの木の生育に適した環境のスマトラ島
コーヒーの木は他の植物と同様に「水」が欠かせません。インド洋から吹き込む湿った空気がバリサン山脈にぶつかり雨雲を生み出し雨をもたらします。これは「地形性降雨」と呼ばれる現象で、年間雨量は東京の年間雨量約1,500mmの1.5倍にも及ぶ2,200〜2,600mmもの雨が降り、この豊富な雨がコーヒーの木を潤します。そして、火山性土壌特有の水はけの良さと適度な保水性が根腐れを起こすことのない条件を作り出しています。
また、この山脈の熱帯雨林は落ち葉や枝が分解されて作られた有機物も豊富に含んでおり、水はけが良いだけでなく土壌の保水性を高め、活発な微生物の活動がさらに土壌を豊かにしてコーヒーの木の成長を助けています。
さらに、火山灰が長年堆積して作られたこの土壌はカリウム、マグネシウム、カルシウムなどのミネラルを豊富に含んでおり、水や栄養とともに吸収され、スマトラ島のコーヒーに独特の深みのある味わいと、スパイシーだったりフルーティーでフローラルな複雑なニュアンスを与えています。

◯収穫からコーヒー豆になるまで
インドネシアではコーヒーチェリーの収穫時期は生産地域によってまちまちですが、主に10月〜3月が収穫時期になります。スマトラ島の場合、雨季の後の9〜12月頃が収穫時期になります。
まずは収穫ですが、完熟したチェリーを手作業で丁寧に摘み取ります。深い赤色または赤紫色の完熟したチェリーだけを選んで摘み取る必要があり、早すぎても遅すぎても最高の味は引き出せません。
次にチェリーの外側を取り除く果肉除去の工程ですが、この工程には主に二つの方法があります。一つはコーヒーチェリーを天日干しにして乾燥してから果肉を取り除く「乾式法」で、フルーティな味わいになります。もう一つは「水洗式法」と言い水を使って果肉を取り除く方法です。こちらは品質が均一になり、味わいもすっきりとしたクリーンな味わいになります。
しかしスマトラ島では「ウェットハル方式」や「スマトラ式」あるいは「セミウォッシュ方式」とも言われる乾式法と水洗式法とのハイブリッドとも言える方法が用いられます。「ウェットハル方式」は高い湿度と雨量が多い地域ならではの方法で、豆を覆う薄皮(パーチメント)を半湿りの状態で取り除くことで乾燥時間が短くなり豆の中心部に水分が残ることで独特の風味を生み出します。
次の発行工程では発酵槽で丸一日かけて豆の周りに残った果肉(ミューシレージ)を分解してコーヒー豆の味わいを引き出します。発酵が終わると水洗いの工程で、雑味の原因となる発酵で分解された果肉の残りや不純物を完全に取り除きます。そして、最後の乾燥工程を経てスマトラ産コーヒーの特徴的な味わいが生み出されます。

◯コーヒー豆にも休息を
乾燥が終わったらすぐに出荷とはなりません。生豆の青臭さを除去するために「レスティング」を行います。レスティングとは豆を休ませる時間のことです。休ませては乾燥させることを約2週間も繰り返して、豆の中の水分を均一にしていきます。この過程がコーヒーの味わいを決める重要な要素になります。
レスティング期間中、豆の中ではゆっくりと酵素が働き、苦味の元になる化合物を分解し、香りの元になる物質を生成するなど複雑な反応が起こっています。また、豆の表面と内部の水分差が徐々に均一化し、豆の内部構造が安定化し、後の焙煎過程でより均一に熱が伝わるようになります。
この過程は地域の気候や環境に大きく影響されます。スマトラ島の高湿度な環境がこのようなゆっくりとしたレスティングを可能にし独特の複雑な風味を引き出しています。乾燥地帯では豆が急速に乾燥しすぎてしまい、同じような効果は得られません。
レスティングの重要性はあまり一般には知られていないので、初めて聞いた方が多いのではないでしょうか。しかし、バイヤーや焙煎士はコーヒーの品質に大きな影響を与えるこの過程の重要性をよく知っているのです。

◯選別から出荷
選別には目的によっていくつかの方法があります。主な選別方法は次のとおりです。
・比重選別:高密度の豆ほど品質が高いので、水や空気を使って豆を選別します。水選機を使って未熟豆や虫食い豆など水に浮く豆(フローター)を取り除き、風選機を使って軽い豆(チャフ)を風で吹き飛ばします。
・スクリーン選別:サイズの均一性が焙煎の均一性につながるため、サイズの異なる金属製の網に乗せて振動を与え小さい豆を落下させ、大きさで豆を分けます。
・ハンドピック:機械では取り除けなかった欠点豆を人の目でチェックして欠点豆を取り除きます。この方法で見つかる欠点豆には黒豆、発酵豆、虫食い豆などがあります。これらを丁寧に取り除くことで、味わいが大幅に向上します。
いよいよ袋詰めです。湿気や酸素を通さず、豆の品質を長期間保持するためにグレインプロバッグ(特殊な多層フィルム袋)を使います。一般的に一袋の重量は60kgです。
出荷前の品質検査も重要です。物理的検査では水分量、密度、粒度分布を、官能検査では味わいの評価を、化学的検査ではカフェイン含有量、酸度を検査します。
これでようやく日本に向けて出荷できます。ただし、日本の残留農薬基準は世界でも厳しいと言われていて、例えばイソプロカルブは0.01ppm以下、カルバリルは0.1ppm以下、グリホサートは5ppm以下という基準となる数値が設定されています。これらの基準をクリアするためには、栽培段階から細心の注意を払う必要があります。除草剤を使わない、有機栽培や減農薬栽培の技術などが重要になります。
また、輸出の際には次の通り複数の書類が必要です。
① 原産地証明書
② 植物検疫証明書
③ インボイス
④ パッキングリスト
⑤ 船荷証券(B/L)
これらの書類をそろえて、やっと日本に向けて出荷されるのです。

一杯のコーヒーが出来上がるまでには、豊かな自然の循環、長年の歴史のなかで培われた農家さんの知恵、そして人間と自然との調和があってようやく出来上がるものだと今回記事を書きながら思い知らされました。ある地方の農園では、周囲に在来種の樹木を植えることで、コーヒーの受粉を助けたり害虫を食べてくれる野鳥や昆虫の生息地を確保していると聞きました。熱帯雨林の保水力を活かしながら土壌の恵みを頂いたり、丁寧な摘み取りや時間をかけて風味を引き出す熟練の技など、自然と人が一体となって作り上げられるインドネシアのコーヒーを魅力を多くの人に知っていただきたいと思います。

















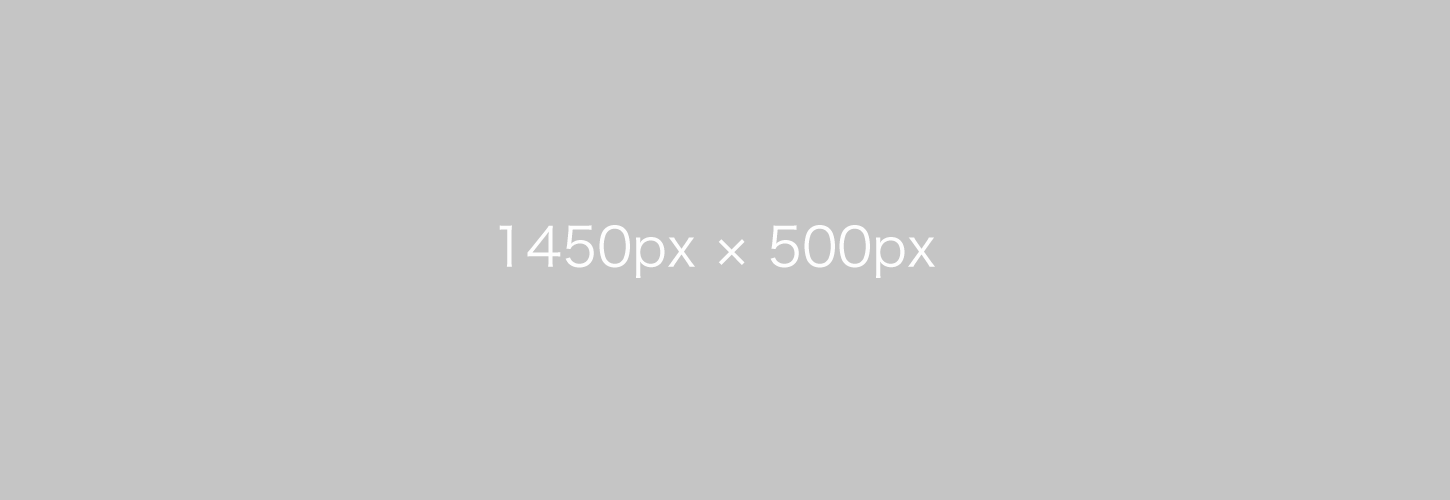
コメント